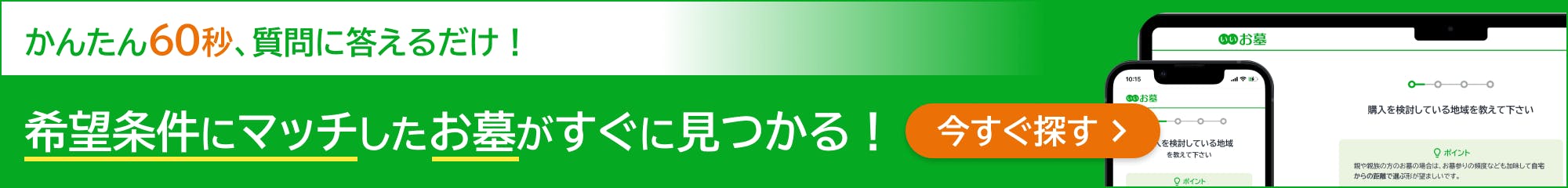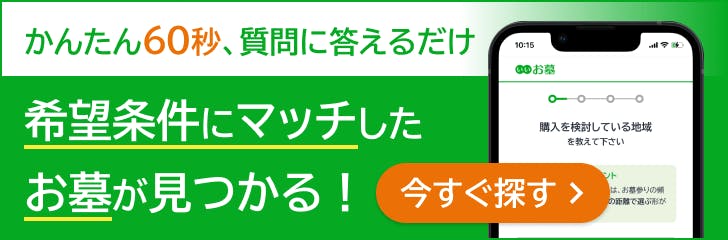現在保存した検索条件はありません。
×閉じる
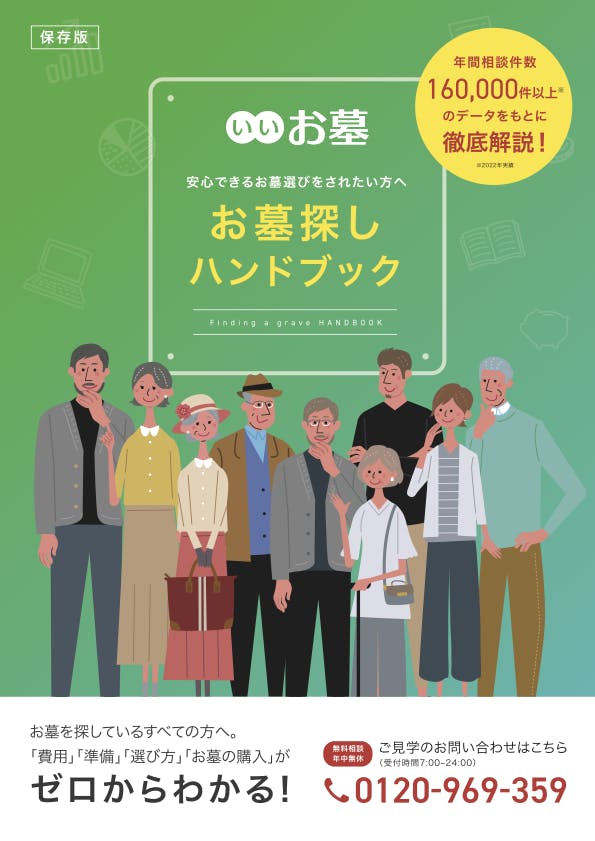
もれなく
全員に
お墓探しに役立つ資料をプレゼント!
ご希望の条件に合ったお墓も合わせてご提案します
「公営霊園」は自治体が運営しており、区画に空きが出ると募集を開始する。応募条件には制約が設けられている場合が多いです。
「民営霊園」は宗教法人や公益法人が運営しており、石材店や不動産会社が販売元になっているケースが多いです。また、公営も民営も宗教的な制限がないケースがほとんどです。
「寺院墓地」はお寺が運営しており、宗教的な制約が課せられるケースがあります。
「共同墓地」は自治会や有志の会が運営しており、地元の人の墓地として存在しているケースです。
営元の宗旨・宗派ではなく、契約予定のお客様の宗教的な制約条件です。寺院墓地で「宗派不問」の場合は、過去の宗旨宗派は問わないが、契約後はお寺の宗旨宗派に準ずる必要があります。
永代供養墓 / 一般墓
ペットと一緒に納骨可能な区画が存在することを示します。対応する販売区画をご参照ください。また、「相談可」のケースもあるため、資料を取り寄せてみることをお勧めします。
お墓を継ぐ人がいなくても、霊園や寺院が永代にわたって遺骨の供養と管理をしてくれます。永代供養とも呼ばれます。
通常、寺院墓地では、檀家(だんか)になる必要があり、お布施や法事など様々な義務が発生します。しかし、寺院墓地でありながら、檀家義務がないケースもあります。
定期運行(毎日、毎週など)、事前予約制、チャーター便などがあり、迎バスの運行時間や料金、予約方法なども、霊園ごとに異なります。また、お盆やお彼岸の時期だけ運行しているケースもあります。
お墓参りの際に利用可能な駐車場を指しますが、寺院墓地の場合は、「檀家専用」となっているケースもあります。見学時に利用不可のケースもあるため、事前に見学予約をお勧めします。
お墓参りの際にバリアフリーに対応しているかどうかです。段差がないフラットな敷地になっているケースをバリフリー対応としている場合が多いです。一部のみバリアフリー対応しているケースもあるため、見学時に対応範囲を確認ください。
故人が亡くなってから一周忌、三回忌などの法要を行うための部屋(法要室)が設けられているケースです。法要では、お坊さんによる読経や焼香を実施し、自宅やお寺で行うケースもあります。
光林寺は大宝元年(701)文武天皇の勅命を受けた徳蔵上人によって、光林寺の南約7Kmの奈良原山山頂にあった蓮華寺と共に開かれた。徳蔵上人は第十五代応神天皇の御世に来朝された弓月君(ゆづきのきみ)の子孫と伝えられ、法相宗(ほうそうしゅう、奈良の興福寺と薬師寺を大本山とする)と、三論宗(さんろんしゅう、現在は東大寺に伝わる)を修めた大徳であったので、開山当初より約百年間程は法相宗と三論宗の二宗兼学の寺であった。光林寺の住持、圓職上人代の大同元年(806)唐より帰国途中の空海上人(弘法大師)が、奈良原山の蓮華寺に登られて密教の修法をされた。また、空海上人(弘法大師)は光林寺にしばらく止住されて密教を伝授されました。これより後、光林寺は法相・三論兼布の寺であったのを密教弘通の真言宗の寺となったと伝えられている。
天長3年(826)空海上人(弘法大師)の奏聞に因り、淳和天皇の勅願として堂塔の建立が開始され、佛閣が整備される事になりました。5年の歳月をかけ天長7庚戌年(830)3月、本堂・金堂・庫裏・客殿・多宝塔・鐘楼堂・仁王堂が完成し、四十九院の根本道場となった。天禄3年(972)回禄の変によって一時灰燼に帰したが、長久3年(1042)後孔雀天皇の勅願により伊予守源頼義公の奉行をえて堂塔の再建が図られた。四十九院は十二坊として再興され、新たに薬師堂も建立された。現存する仁王堂は源頼義公によってこのときに建てられたもの。これらの十二坊は、この後規模を大きくしながら南北朝時代まで法灯が続いたもようなものだ。永禄元戊年(1558)には、河野伊予守四郎通直公により旧慣を尋ねて堂塔の修復がなされました。元禄十四年(1701)には、光林寺開山一千年に当たり、今治城主松平駿河守定陳公によって新たに本堂が再建されました。これが現在の本堂である。
光林寺は、特に南北朝時代の大波、明治初めの神仏分離の大波などを受けながら、1300年の歴史を歩んでいる。
薔薇や桜など植栽されている。又ごみ置場水まわりなど近くに設置されトイレもきれいな所。
日当たりは良くて、景色はいい。季節によっては、お花がきれいでいい
山の中の静かなお寺です。去年、墓園とは別に納骨堂が完成しました。
光林寺の地図、最寄り駅や交通アクセス、霊園の施設に関する情報をご案内します。
exploreMAPで周辺霊園を探す
周辺にどんなお墓があるか
見てみませんか?
JR予讃線 伊予富田駅
JR予讃線 今治駅
JR予讃線 大西駅
「いいお墓」では、墓じまいから改葬(お墓の引越し)のサポートもしております。工事や手続きが必要ですので、検討されている方はお墓のお引越しサービスも是非ご確認ください。
まずは費用の目安を知るLINE登録でかんたん見積り! さらに詳しく見る費用相場や施工事例はこちら