現在保存した検索条件はありません。
×閉じる
日程を選択して今すぐ見学予約
その他の日程を選ぶ「公営霊園」は自治体が運営しており、区画に空きが出ると募集を開始する。応募条件には制約が設けられている場合が多いです。
「民営霊園」は宗教法人や公益法人が運営しており、石材店や不動産会社が販売元になっているケースが多いです。また、公営も民営も宗教的な制限がないケースがほとんどです。
「寺院墓地」はお寺が運営しており、宗教的な制約が課せられるケースがあります。
「共同墓地」は自治会や有志の会が運営しており、地元の人の墓地として存在しているケースです。
営元の宗旨・宗派ではなく、契約予定のお客様の宗教的な制約条件です。寺院墓地で「宗派不問」の場合は、過去の宗旨宗派は問わないが、契約後はお寺の宗旨宗派に準ずる必要があります。
合祀墓 / 永代供養墓
ペットと一緒に納骨可能な区画が存在することを示します。対応する販売区画をご参照ください。また、「相談可」のケースもあるため、資料を取り寄せてみることをお勧めします。
お墓を継ぐ人がいなくても、霊園や寺院が永代にわたって遺骨の供養と管理をしてくれます。永代供養とも呼ばれます。
通常、寺院墓地では、檀家(だんか)になる必要があり、お布施や法事など様々な義務が発生します。しかし、寺院墓地でありながら、檀家義務がないケースもあります。
定期運行(毎日、毎週など)、事前予約制、チャーター便などがあり、迎バスの運行時間や料金、予約方法なども、霊園ごとに異なります。また、お盆やお彼岸の時期だけ運行しているケースもあります。
お墓参りの際に利用可能な駐車場を指しますが、寺院墓地の場合は、「檀家専用」となっているケースもあります。見学時に利用不可のケースもあるため、事前に見学予約をお勧めします。
お墓参りの際にバリアフリーに対応しているかどうかです。段差がないフラットな敷地になっているケースをバリフリー対応としている場合が多いです。一部のみバリアフリー対応しているケースもあるため、見学時に対応範囲を確認ください。
故人が亡くなってから一周忌、三回忌などの法要を行うための部屋(法要室)が設けられているケースです。法要では、お坊さんによる読経や焼香を実施し、自宅やお寺で行うケースもあります。
近鉄奈良駅の南、歴史的町並みが広がる「ならまち」の東南に佇む璉珹寺。聖武天皇の発願で行基菩薩が開いた紀寺の跡と伝わり、前身は飛鳥にあったと伝えられる由緒あるお寺です。本尊の阿弥陀如来立像(県指定文化財)は、美しい袴をお召しになった大変珍しい木造白色の女身の裸形像で、鎌倉後期の作と伝えられています。また脇侍の木造観音菩薩立像は奈良時代、木造勢至菩薩立像は室町時代の作で、どちらも重重要文化財に指定されています。
5月には境内にニオイバンマツリ(匂蕃茉莉)が咲き誇り、まるで阿弥陀如来様が傍で見守って下さっているような気持ちになる甘い香りに包まれます。このほかメキシコ万年草や大山蓮華など四季折々の花々が境内を彩ります。
■永代供養塔
本堂横、泰山木の下にお祀りしています。
春秋彼岸・お盆には墓前にて回向を行います。
お参りは時間に関係なく自由にお参りできます。
宗派を問わずご利用いただけます。
納骨永代供養をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
※3年以内の口コミを要約しており、口コミ投稿時と現在の状況は異なる場合がございます
総合評価
購入価格15.0万円
静かな場所、穏やかな雰囲気、綺麗な納骨堂、交通便などを考えて総合すると良心的な料金であると思います。
自宅からは車がなければバスの乗り換え、電車の乗り換えなどが必要でありやや不便ではないのかと思います。
お寺の場所は、街中であるにもかかわらず車の音も気にならずとても静かであり年中花や緑があって落ち着けるところです。
お寺の門を入ると開放感があり明るいです。花や緑が多くこじんまりとしたお庭もあります。 建物の古さには威厳を感じます。阿弥陀様の近い場所に納骨堂があり安心して過ごせそうに感じました。
納骨堂の周りにはお墓がありますが太陽の陽を浴びてとても明るく陰気なイメージはありません。お参りしやすいです。
総合評価
購入価格60.0万円
見学に行った時点では、永代供養墓にしては少し高めかなと思っていたが、納骨の際の読経なども全て込みということがわかり、お参りしやすさ、お寺さんの親しみやすさなども総合的にみて、とても良いところに落ち着けたと満足しています。
道が狭くクルマで行くのはやや困難ではあるが、バスは廃止や減便の心配のない市内循環系統の内回り・外回りの両方が利用可能です。JR奈良駅からだと内回りで8分、外回りで20分。便数も多いので、JR奈良駅や近鉄奈良駅周辺へ出掛けた際に気軽に立ち寄ることもでき、この先、歳をとってクルマに乗れなくなっても安心です。
奈良旧市街の外れにあるお寺は通りからやや奥まったところにあり、中に入るととても静かです。周囲にあまり高い建物がないため墓地エリアの日当たりは良く、永代供養墓も南向きで明るい場所にあります。お墓といっても陰気な感じはありません。
永代供養墓の石塔(裏は納骨室への入口になっているらしい)はシンプルなデザインですが、過度の装飾がないところがかえって好感が持てます。前面にはお参りするためのスペースが十分とられています。街中のお寺さんの墓地なので郊外の霊園墓地のような便利な設備はありませんが、通常はお参りを済ませれば直ぐに帰るでしょうから問題はないと思います。どうしても必要なときはご住職にお声掛けすれば融通も利くと思います。
お寺も墓地エリアもよく手入れされていて清潔感があります。特に墓地エリアは昔からの檀家さんのお墓というより比較的近年に整備されたらしく、整然としていて綺麗です。
総合評価
近くにバスは止まりますが電車の最寄り駅からは少し離れていますし駐車場はございませんでした。またお寺の見つけやすさは初めて行く方には2件隣にもお寺がございますので間違うかも知れません。私は間違えてしまいました
敷地内は凄く広くお墓がある場所は日当たりが抜群でお墓一つ一つ奇麗にされていて敷地内も自由に出入り出来ますのでご身内の方だけではなく隣近所の方々がお参りに来るらしく雰囲気は良いと思います
法要施設内は広くそしてエアコンも完備されていませんが夏なのに窓を全開に開け扇風機だけでしたが涼しげでのんびりと時間が過ぎて行きました。凄く素敵でした
女性の住職が1人で全てやっているとの事ですが穏やかな人柄でお寺の歴史やご自身の過去の話をされ住職と言うか人として魅力があり優しい方でした。園内には色んな果物が出来る木が立っていて時期や季節により園内の景色が変わるそうで清掃も毎日お一人でされているらしく奇麗でした。時々鹿が勝手に入り込み荒らしていくそうですが・・・
街中であるにも関わらず静かな環境で落ち着きます。お花が沢山あり明るい感じです。お墓の場所も陽の光がさして暗いイメージはありません。大きなお寺では無いので静かにお参りできそうですね。
璉珹寺 永代供養墓の地図、最寄り駅や交通アクセス、霊園の施設に関する情報をご案内します。
exploreMAPで周辺霊園を探す
周辺にどんなお墓があるか
見てみませんか?
大和路線 奈良駅
奈良線 奈良駅
近鉄奈良線 近鉄奈良駅
「いいお墓」では、墓じまいから改葬(お墓の引越し)のサポートもしております。工事や手続きが必要ですので、検討されている方はお墓のお引越しサービスも是非ご確認ください。
まずは費用の目安を知るLINE登録でかんたん見積り! さらに詳しく見る費用相場や施工事例はこちら




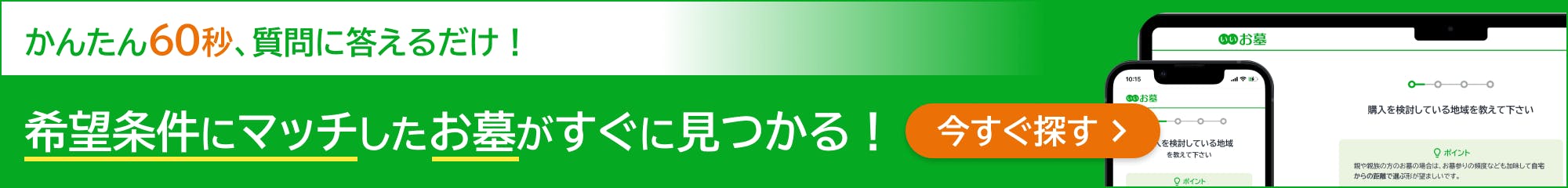
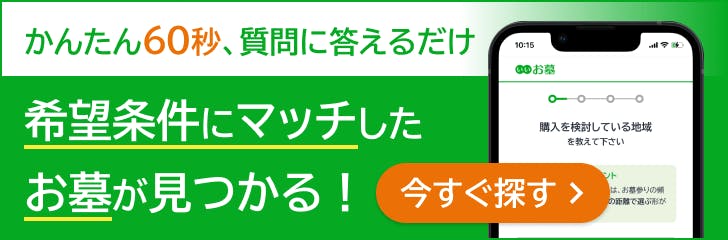
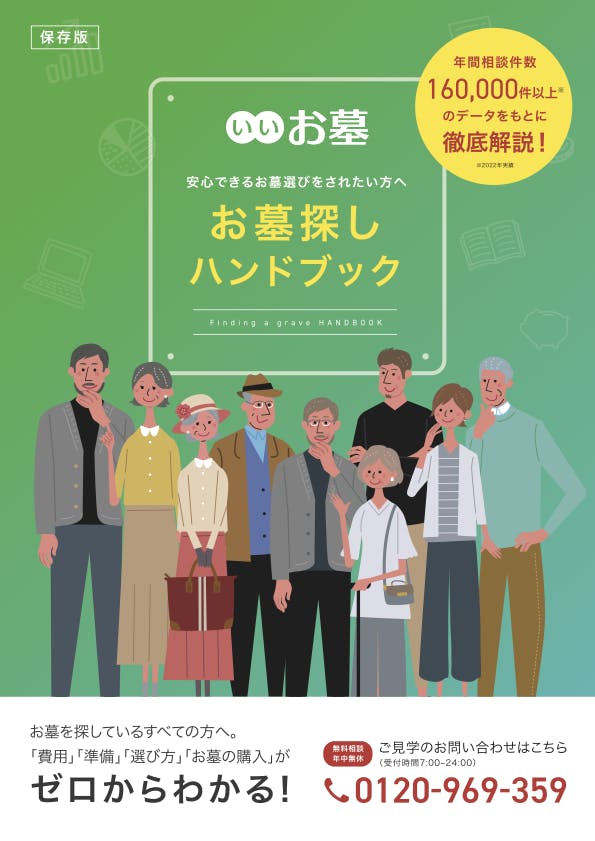
もれなく
全員に
お墓探しに役立つ資料をプレゼント!
ご希望の条件に合ったお墓も合わせてご提案します